-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
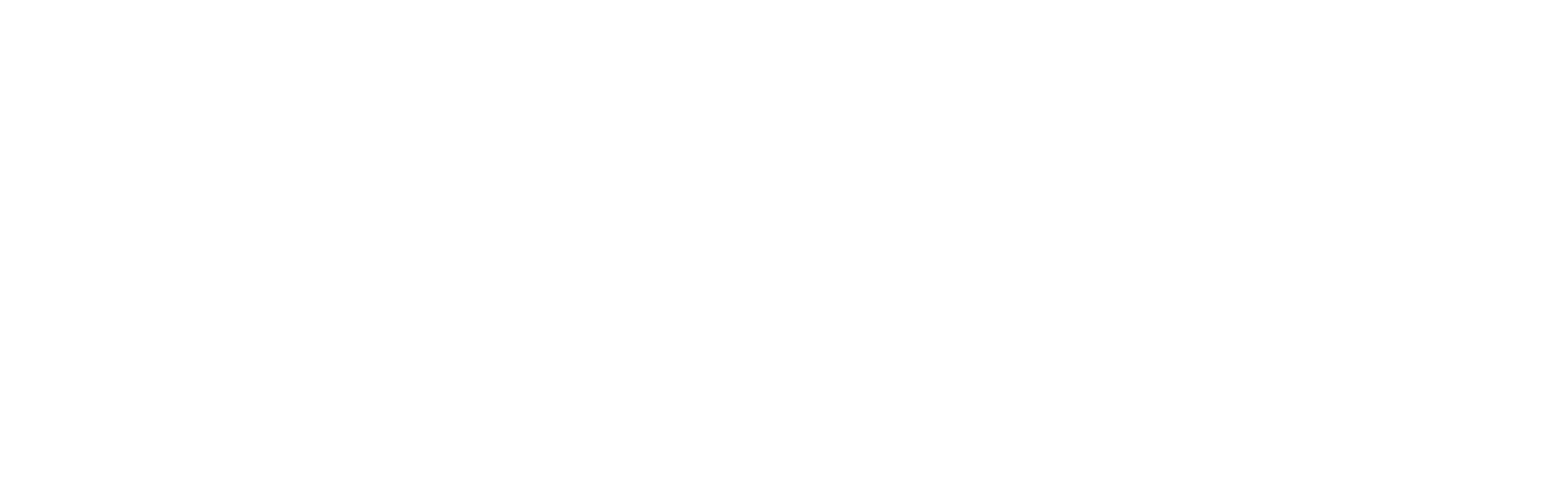
皆さんこんにちは!
金色、更新担当の中西です。
さて今回は
~つくねの黄金比~
皮(脂):保水・コク・口溶けを付与。脂が少ない胸挽きの“潤滑油”。
軟骨(食感):噛み始めの小気味よいコリッと感→咀嚼回数が増え、旨みの滞空時間が伸びる。
胸挽き(ベース):臭みが少なく、澄んだ出汁を壊さない。タンパク質の“骨格”。
(配合は総肉量に対する重量%。例:合計1,000gなら「85/10/5=胸850g・皮100g・軟骨50g」)
| 用途 | 胸挽き | 皮 | 軟骨 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 水炊き(澄んだ旨み重視) | 85 | 10 | 5 | 出汁を濁らせず、ほどよいコクと“コリ”。 |
| 鍋でも主役(コク厚め) | 80 | 15 | 5 | 白濁寄りの鍋や味濃い薬味向き。 |
| 焼き(つくね串) | 70 | 20 | 10 | 高温乾燥に耐えるジューシー設計。 |
| スープ団子(超あっさり) | 90 | 5 | 5 | 軽やか、朝食や〆椀向き。 |
目安:皮10〜15%、軟骨5%前後が“水炊き”の安全地帯。皮が多すぎると浮き脂が増え、軟骨が多すぎると一体感を損ねます。
胸挽き 850g
鶏皮 100g(下茹で→氷水→水気を拭き、5mm角)
ヤゲン軟骨 50g(2〜3mm微塵。尖りは取り除く)
塩 1.3%=13g(最初に入れて**2〜3分“塩すり”**して粘りを出す)
おろし生姜 10g、長ねぎ微塵 50g
卵白 1個分(約30g)※臭みなく弾力アップ
片栗粉 2%=20g(保形性/鍋にパン粉は入れない)
氷水 or 出汁 8〜10%=80〜100ml(温度を上げず保水)
好みで:薄口醤油 5〜8ml、酒 10ml(香りの下支え)
ポイント:粉→液体の順だとダマになりにくい。常に5℃以下で仕込み、ボウルは氷当て。
皮と軟骨の下処理
皮はサッと下茹でして脂と臭みを落とす/軟骨は細かくして角を取る。
塩すり(タンパク抽出)
胸挽き+塩を先に混ぜ、粘り(糊化感)が出るまで混ぜる。
結着・水分・具材投入
卵白→片栗粉→氷水→生姜・葱→皮・軟骨の順に低温で均一化。
火入れ
85〜90℃の出汁で“湯ポチャ”。沸騰はさせない(脂が分離・硬化の原因)。中心温度75℃1分で安全域。
もっとジューシーに:皮+2〜3%、氷水+2%(ただし出汁が濁りやすくなる)
プリッと弾力:塩を1.4〜1.5%に上げ、卵白+10g、練り時間+30秒
コリ感強化:軟骨+2%(2mm未満の刻み厳守)
軽やかに:皮▲3%、氷水+2%、片栗▲0.5%
パサつく → 皮+2% or 氷水+2%、火入れ温度を**85〜90℃**に下げる
ボソつく → 塩すり不足。塩を最初に入れて粘りが出るまで混ぜ直す
崩れる → 片栗+0.5〜1%、卵白+10g、成形後5分休ませる
脂が浮き過ぎ → 皮▲3%、下茹で時間+30秒、沸騰禁止
軟骨が固い/痛い → 刻み粗い。2〜3mm厳守、尖り廃棄
1袋100g×4パターン(皮8/10/12/15%)を作り、85℃で同条件3分火入れ。
重量減少率(ドリップ)
官能(ジューシー・コリ感・一体感を5段階)
出汁の濁り指数(主観でOK)
→ スタッフ3名の中央値で次回配合を決定。**“自店の黄金比”**はここから生まれます。
仕込み温度10℃以下・速やかに成形/保管は4℃以下、当日使い切り。
垂直交差汚染防止(生用具と加熱済用具の色分け)。
中心温度75℃1分確認。鍋で長置きしない。
1巡目は小さめ(15g)で軽く、2巡目はやや大きめ(25g)でコクを増やす。
終盤に数個追加→雑炊のコク種として機能させると、〆が一段豊かに。
水炊きの黄金比=胸85|皮10|軟骨5%(塩1.3%・水分8〜10%)。
塩すり→低温管理→85〜90℃火入れが三種の神器。
微調整は2〜3%幅で一要素ずつ。ABテストで“自店の正解”を数値化しましょう。
![]()
皆さんこんにちは!
金色、更新担当の中西です。
さて今回は
~こだわり~
水炊きは、塩と柑橘、時に自家製ポン酢——調味は極めて最小限。
だからこそ主役の“鶏”が持つ 香り・コク・余韻 が、そのまま椀の中に現れます。私たちの仕事は、味を“足す”のではなく、潜んでいる旨みを邪魔しないこと。
品種と月齢
若鶏の柔らかさと、*親鶏(ひね)*の深いコク。それぞれの長所を料理で使い分けます。
例)出汁は親鶏ガラで骨太に、身は若鶏でしっとり。鍋の中で役割分担させる設計です。
餌と環境
脂の質=後味に直結。穀物主体で香りが澄むもの、ハーブ飼料で脂が軽くなるものなど、飼料設計が“後味”を決めると考えています。
締め方と冷却
放血の丁寧さは雑味、急速冷却はドリップの少なさに比例。解体〜冷却の管理がスープ濁りのカギになります。
枝肉の休ませ
解体直後は筋が張るため、0〜2℃で一晩。水分と旨みを内部に戻し、繊維のギスギスを取ります。
部位ごとの下ごしらえ
胸は低温火入れ用に整形、モモは繊維に沿って余剰筋を処理。骨はあらい湯で血と脂を抜き、香りを澄ませる——ここを怠るとスープが重くなります。
白濁(パイタン):骨と皮のコラーゲン・脂・可溶性たんぱくを対流で乳化。力強い旨みと粘度で、口当たりに“厚み”を。
清湯(チンタン):弱火で香りを逃さず引き出す。余分な脂・灰汁をこまめに掃除して、雑味のない透明感を追求。
→ 当店は 清湯でスタート→途中で白濁を合わせる“二段仕立て”。前半は滋味、後半は力強さ。鍋の中で味が“育つ”設計です。
ガラ:背ガラで骨格の出汁、モミジでゼラチンの“のり”、手羽元で香りの芯。
身:モモ=ジューシー、胸=品の良い甘み、ササミ=繊維のほどけ。
つくね:ミンチに刻み軟骨と皮目の脂をブレンド。スープの中で旨みを“放出する部位”として機能させます。
内臓:新鮮な肝・ハツを“ごく短時間”泳がせ、香りを移してから別皿へ。香りはスープへ、身は刺さず最後に。
塩:立ち上がりは鉱塩の角で輪郭を作り、仕上げは海塩の甘みで丸める。塩は味を“足す”のではなく、鶏の甘みを前に出すスイッチ。
水:硬度は旨みの抽出速度に影響。中軟水を基準に、季節でスープの滞空感を微調整します。
コールドチェーン:受け取り→分割→仕込みまで10℃以下の冷蔵導線を徹底。
交差汚染ゼロ:生と加熱済みの動線・器具・保管を完全分離。色分けまな板・包丁は厨房の“信号機”。
記録:温度ログ、ロット、調理工程を日々記録。美味しさは“再現できること”で担保されます。
夏:脂を軽く、清湯比率を高めて“するり”と。柑橘を強めに。
冬:皮やモミジを厚めに配分、粘度と保温性を優先。薬味は生姜ベースで体を温める。
新物の時期:若鶏主体で軽快に、親鶏ガラは控えめにして香りを前へ。
前日夕方:ガラ下処理→一番出汁(清湯)抽出→冷却
当日朝:白濁スープ炊き上げ→ブレンド比率決定→塩水調整
営業前:部位分け・つくね練り・薬味仕込み
営業中:鍋は清湯で提供開始→食べ進めながら白濁を追い足し→〆雑炊でコラーゲンを封じる
ガラを熱湯で短時間くぐらせて血と脂を落とす。
最初は弱火で清湯、途中から強めに対流させて白濁を少しだけ。
塩は最後に。味が“整った瞬間”で止めるのがプロの勘。
水炊きは、鶏の生い立ち、処理、熟成、部位設計、火の入れ方、塩と水——無数の小さな意思決定の積み重ねです。
“派手さ”はないけれど、椀から立つ湯気に鼻を近づけた瞬間、鶏の輪郭がくっきりと立ち上がる。
その一口のために、今日も鶏に正直であり続けます。
![]()